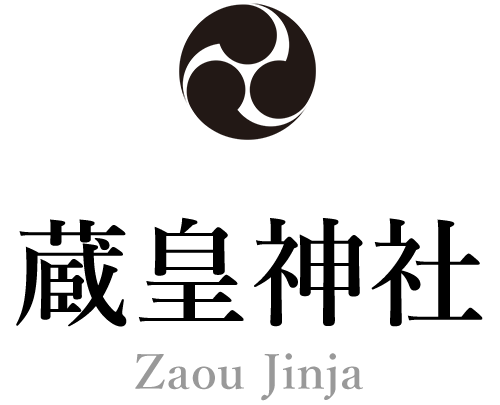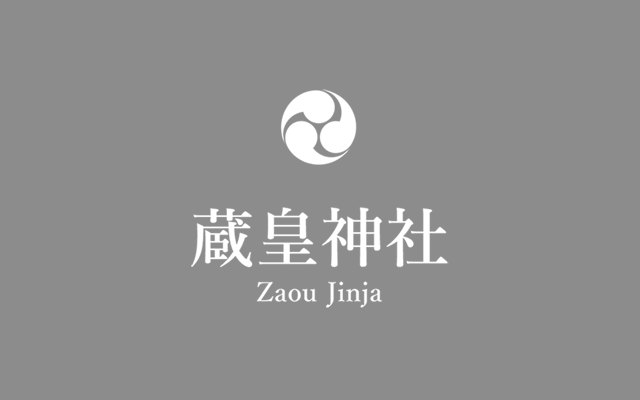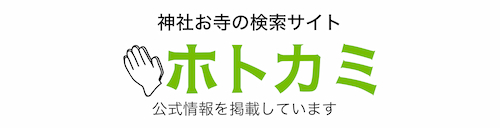古来より、「虫切」「厄除」「方除け」の神様として広く信仰されてきた藏皇(ざおう)神社。
主祭神には広国押武金日尊(ひろくにおしたけかなひのみこと)【第二十七代 安閑天皇】をお祀りしています。
また、藏皇神社では、古くから蔵王権現(ざおうごんげん)を守護神と仰ぎ、蝦夷の侵攻を防いだ神として「厄除け」「方除け」の信仰が篤く行われてきました。
棚倉藩主の嗣子が病弱であった際、蔵王権現に祈願したところ健やかになったと伝えられ、これにより「虫切」の祈願として遠近より多くの参拝者が訪れ、親しまれてまいりました。
後の祭神には金山彦神(かなやまひこのかみ)をお祀りしております。
金山彦神は古来より鉱山、金属、鍛冶を司る神様として崇敬され、鉄や銅をはじめとした金属の採取・精錬・加工の守護神と仰がれてまいりました。
当社周辺では、かつてたたら場や勿来炭鉱が栄え、金山彦神への信仰は地域の鉱業・金属産業の発展を支える大きな精神的支柱となっておりました。
人々は金山彦神に事業の繁栄、工匠の技術向上、安全無事故を祈願し、深い感謝と畏敬の念をもって祀り続けてきたと伝えられています。
近年では、金属すべてに関わる神様であることから、商売繁盛や金運向上、さらには人との縁や新たな道を開く力を授けてくださる御神徳があるともいわれ、参拝者が願いを込めて足を運んでおります
地域では「蔵皇(ざおう)さん」「蔵皇さま」と呼ばれ、氏神・鎮守様として虫切り、厄除け、安全祈願に多くの人々が訪れています。
長い歴史を引き継ぎ、山桜や大銀杏の四季が感じられる憩いの場所として、これからも地域の皆様に親しまれ続けることを願っております。
【蔵皇神社の歴史】
明治初期の神仏分離政策を背景に、神道が国教として位置づけられる中、「蔵皇神社」として新たな歩みを始め、以来、今日に至るまで人々の信仰を大切に守り続けております。
人と人とが心を通わせる神聖な場所として、これからも永く人々に敬われ、受け継がれていくことでしょう。
【例祭日】
十月 体育の日
【摂・末社】
若宮八幡神社(お祭り:四月八日)
蔵王権現社(お祭り:一月二十八日)
阿夫利神社